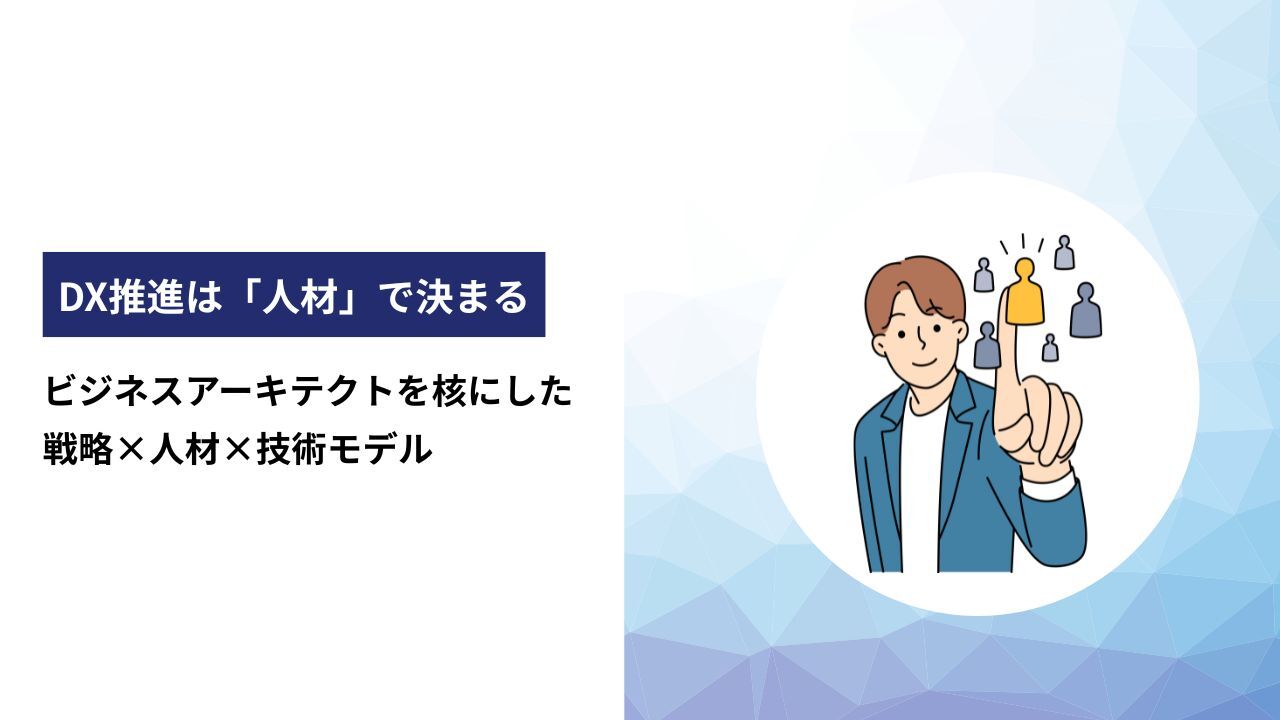DX推進は「人材」で決まる──ビジネスアーキテクトを核にした戦略×人材×技術モデル
DXを中期経営計画に掲げつつも、「何から手を付ければ良いのか」「投資対効果が見えない」とお悩みではありませんか。実は、多くの企業でDX推進が思うように成果に結び付かない背景には、技術ではなく人材と組織の課題があります。
本記事では、DX推進の全体像と成功のためのフレームワークをわかりやすく解説し、具体的な推進ステップやKPI設計、必要な人材像、失敗パターンの回避策まで実務に役立つ情報を網羅します。最後までお読みいただくことで、自社のDXロードマップを描き、効果的なリスキリング施策に着手するヒントをつかんでいただけるでしょう。
目次
DX推進の現状と課題
まず、日本企業のDX推進の現状を俯瞰してみましょう。近年、多くの企業が業務のデジタル化に取り組み始めています。しかし「デジタル(技術)は進み始めたが、トランスフォーメーション(事業変革)は進んでいない」と指摘されています。
事実、IPAの「DX白書2023」によれば、DXに取り組む日本企業のうち「成果が出ている」企業は6割弱にとどまり、米国企業の約9割に比べ大きな差があります。この原因の一つは、人材育成や組織改革が追いついていないことです。
例えば、DXを支えるIT人材の多くがベンダー企業所属で、自社内でDXを推進できる人材が不足している傾向があります。日本企業ではコア業務のIT開発を内製できている割合が24.8%にすぎず、多くを外部に依存しているというデータもあります。これは裏を返せば、自社人材のデジタルスキル不足と人材育成の遅れを意味します。
こうした中、DX施策の成果が出ない最大の要因として注目すべきなのが「研修と実務の乖離」です。パーソルイノベーションの2025年調査でも、企業のリスキリング施策における失敗例の第2位に「研修・学習内容が実務にマッチしていなかった」が挙がりました(35.6%)。研修で学んだことを現場で活かせなければ、せっかくの人材育成投資もROIに繋がりません。
出典:リスキリングレポート〜リスキリングによる報酬変化と生成AI(ChatGPT等)活用の最新状況〜【2025年3月版】_24P
さらに「従業員任せで推進されず成果に繋がらなかった」(38.2%)や「習得したスキルを実践する場がなかった」(31.8%)といった声もあり、組織として体系立った支援や環境整備が不足している現状が浮き彫りです。
このように、DX推進のボトルネックは人と組織にあると言えます。DX成功には最新技術の導入以上に、経営のコミットメントによる組織改革と人材育成戦略が不可欠です。では、具体的にどのように進めればよいのでしょうか。次章から、DXを成功させるためのフレームワークと実践ポイントを解説していきます。
DX成功に向けた6つの要素
DXを推進し成果を出すためには、包括的なフレームワークに沿って取り組むことが重要です。単発のIT導入や研修で終わらせず、組織全体を変革する視点が求められます。以下に、DX成功のポイントとなる6つの要素を示します。
経営主導のリーダーシップ
DX推進にはトップの強いコミットメントが必要です。経営層自らがビジョンを示し、DX推進室やプロジェクトに権限とリソースを与えて率先垂範する体制を整えます。現場任せにしないトップダウンの支援が、社内の意識改革と横断的な協力を生みます。
明確な目的とKPI設定
DXを通じて「何を実現したいのか」というゴールを明確化し、定量的なKPIを設定します。例えば「業務プロセスの効率化による生産性〇%向上」や「新規デジタルサービス売上〇億円」など、ビジネス成果に直結する指標を掲げましょう。
KPIは現場レベルまで分解し、各部門・チームが自分事として取り組めるようにします。進捗は定期的にモニタリングし、達成度合いに応じて戦略を軌道修正することで、投資対効果を可視化できます。
多様な研修アプローチの組み合わせ
従業員のスキルや役割に応じて、研修方法を多面的に設計します。オンライン講義やワークショップ型研修、現場でのOJT、ハッカソンや実践プロジェクト参加などを組み合わせ、アウトプット重視の学習を促進します。
座学で知識インプットだけでなく、実際に手を動かし課題解決する場を設けることで、「学んだけれど使えない」を防ぎます。多様なアプローチにより、幅広い人材の学習スタイルに対応し、定着率を高めます。
適切なリソース配分と支援
DX推進には時間・人員・予算といった経営資源の投入が不可欠です。日常業務と並行して新しいプロジェクトに取り組む社員を支援するため、業務の棚卸しや外部リソース活用によって学習時間を確保する工夫も必要でしょう。
社内にDX推進を専任で支える横断チームを設置し、各部門と調整しながら推進する体制(PMO的な機能)を整備します。また、最新ツールや外部専門家の活用に投資し、現場が円滑にDX施策を進められるようバックアップします。
成果の評価とフィードバック
設定したKPIに基づき、DX施策の進捗と成果を定期的に評価します。成功事例は社内で共有し称賛することで社員のモチベーションを高め、失敗例からは学びを抽出して改善策を講じます。単に結果を評価するだけでなく、プロセスもレビューしてフィードバックを行うことで、次の施策に活かします。
例えば「新しいデータ分析ツール導入で処理時間が〇%短縮された」「オンライン接客導入後、顧客満足度が向上した」など、具体的な効果を数値で示し、経営層と現場双方にフィードバックすることが重要です。PDCAサイクルを回しながら、DX推進を継続改善していきます。
学習者のサポート環境整備
DX人材を育成するには、個人任せにしない環境づくりが欠かせません。コーチングやメンター制度を導入して学習フォローを行ったり、社内コミュニティや勉強会で横のつながりを作って情報共有・励まし合いができる場を提供しましょう。
実務と学習の両立を支援するための運営サポートも重要です。例えば、研修の案内やリマインドを行う事務局を設けたり、上司が部下の学習状況を把握して業務負荷を調整したりといった施策です。環境面のサポートによって、社員が安心して学び続けられる文化を醸成できます。
DX推進のステップとKPI設計
DX推進は一朝一夕に完了するものではなく、段階的なアプローチが有効です。ここでは、一般的なDX推進のステップを5つに分けて解説します。
現状評価とビジョン策定
まず自社の現状を把握します。業務プロセスの課題やIT活用度、社内のデジタル人材状況を棚卸ししましょう。
その上で3〜5年後を見据えたDXのビジョン・目的を明確化します(例:「データ活用で意思決定を高度化し、新規サービス創出につなげる」など)。この段階では外部環境の分析(競合他社のDX動向、市場トレンド)も行い、自社が取り組むべきDX領域を定めます。
戦略立案とロードマップ策定
ビジョン実現のためのDX戦略を立てます。ビジネスモデルや業務フローのどこをどう変革するか、優先順位を付けましょう。短期で実行可能な施策と、中長期での大きな変革テーマを整理し、ロードマップに落とし込みます。
例えば「まず営業プロセスのデジタル化を半年で実施→次に顧客データ統合基盤を1年で構築→将来的にデータ分析による新サービス開発」というように段階ごとの計画を策定します。この際、それぞれの段階でのKPI目標(例:〇〇システム導入完了、顧客データ100万件蓄積など)も設定しておきます。
体制構築と必要人材のアサイン
戦略実行のための推進体制を整備します。社内にDX推進プロジェクトチームや専門部署(DX推進室など)を発足させ、各部門からメンバーを集めたクロスファンクショナルチームを編成します。
また、必要なスキルを持つ人材をアサインまたは外部から招へいします。社内に不足するスキルがあれば、人材の採用や社外パートナー企業との協業も検討しましょう。ここで、人材育成計画(リスキリング計画)も並行して策定します。誰にどのスキルを習得させるか、研修計画とOJT計画を明確にし、予算とスケジュールを決めます。
施策実行(PoCと展開)
具体的なDX施策を実行に移します。はじめはPoC(概念実証)やパイロットプロジェクトで小さくテストし、効果や課題を検証しましょう。例えば、新しいAIツールを一部部署で試験導入し、業務効率がどれだけ向上するか検証する、といった具合です。
PoCの結果を受けて必要に応じ改良し、効果が確認できたら全社展開・本格導入に移ります。この段階で重要なのは、成功体験を社内に創出することです。
小さくても成果(例:RPA導入で月○時間の業務削減)が出れば、それを社内広報し社員の理解と賛同を得ます。徐々にDX施策を横展開し、組織全体に浸透させていきます。
定着化と継続的改善
導入したデジタル技術や新しい業務プロセスを現場に定着させます。新しいオペレーションについて社員への追加トレーニングを行ったり、マニュアル整備・ナレッジ共有の仕組みを作ったりしましょう。
定着状況をモニタリングし、現場からのフィードバックを収集して、必要なら運用フローやシステムを改善します。同時に、DX推進によるビジネス成果(KPI)の測定を継続します。
達成したKPIは次の目標設定へとつなげ、DX推進を継続的なサイクルとして回していきます。環境変化に合わせて新たなDX課題が生じた場合は、再びビジョンや戦略をアップデートし、次のサイクルへ移行します。
KPI設計のポイント
上記ステップごとに設定したKPIは、先行指標と成果指標の両面から設計すると効果的です。例えば「◯◯システム導入完了」は先行指標、「処理時間△%短縮」は成果指標という具合に、活動の実行状況とビジネス成果の両方を測りましょう。
また、KPIは経営層の視点だけでなく現場レベルの指標も含めます(例:営業現場なら「商談のオンライン化率◯%」「顧客提案回数◯回増加」など)。これにより、全社のDX進捗を多面的に把握でき、各層で自分たちの貢献が見える化されます。
KPIの達成度合いは四半期ごとなど定期的にレビューし、未達の場合は原因分析して施策を調整します。ROI(投資対効果)についても、中長期で測定可能なように初期段階で指標を設定しておくとよいでしょう。
例えば「DX投資額に対する収益改善額」や「育成コストに対する生産性向上効果」といった指標です。これにより、経営陣へDXの価値を説明しやすくなり、さらなる投資判断も得やすくなります。
DX推進を支える人材と組織づくり
DXを成功させるには、「人」の力が最重要ファクターです。どんな最新技術も、それを活用しビジネス価値を生み出すのは人材だからです。ここでは、DX推進に必要な人材のタイプと組織体制、そして変革を支えるマネジメントについて説明します。
必要な人材類型とスキルセット
経済産業省の「デジタルスキル標準」では、DXを推進する人材を5つの人材類型に分類しています。具体的には以下の通りです。
ビジネスアーキテクト
DX戦略の企画立案やビジネスモデル改革をリードする人材です。業界動向や自社事業への深い理解を持ち、デジタル技術でどのように新価値を創出できるかを描きます。戦略策定力とプロジェクト推進力が求められます。
デザイナー
サービスやプロダクトのユーザー体験を設計する人材です。UI/UXデザインや業務プロセス設計のスキルを持ち、使いやすく付加価値の高いデジタルサービスを形にします。DXでは顧客体験の向上が重要なため、デザイナーの役割は欠かせません。
データサイエンティスト
データの分析・活用を担う専門人材です。ビッグデータやAIを駆使して意思決定に役立つ洞察を導き出したり、予測モデルを構築したりします。DXでは業務や顧客のデータ活用が肝となるため、高度な分析力と統計・機械学習の知識が必要です。
ソフトウェアエンジニア
デジタルシステムやアプリケーションを開発・運用する技術者です。クラウドやモバイルアプリ、RPAなどを活用して業務を自動化・効率化する実装力が強みです。DXではビジネス要件を技術で解決する橋渡し役として重要です。
サイバーセキュリティ人材
デジタル化に伴うセキュリティリスクに対処する専門家です。システムの脆弱性対策、ネットワークセキュリティ、情報漏洩防止など、DX推進に不可欠な安全基盤を支えます。セキュリティはDX成功の土台であり、この分野のスキルも重視されます。
出典:デジタルスキル標準 | 経済産業省
組織横断の推進体制
DXは一部門だけでなく全社横断の変革です。そのためには、組織の枠を超えた推進体制と、変革をスムーズに進めるチェンジマネジメントが重要になります。
まず体制面では、前述の通り経営直下にDX推進の専任組織を置きつつ、各現場部門と連携するハイブリッド型のチームを構築します。例えばDX推進室が全社方針を策定・支援し、各事業部ごとにDXリーダーを任命して現場プロジェクトを動かす、といったモデルです。IT部門と業務部門が二人三脚で取り組む体制づくりもポイントです。
システム開発を外部に丸投げせず、内製できるところは内製し(重要なノウハウは社内に蓄積)、足りない部分は専門ベンダーと協働することで効率と知見の両立を図ります。この内製と外部活用のバランスを取ったハイブリッド体制は、DX推進におけるリスク分散とスピード向上につながります。例えば、基幹システム開発は外部パートナーに任せつつ、自社ではデータ分析や業務改善アイデア創出の部分に注力するといった分担も一案です。
チェンジマネジメント
次にチェンジマネジメントです。新しい取り組みを社内に根付かせるには、人の心理的抵抗や組織文化の壁を乗り越える必要があります。そのために有効なのが、経営トップからの強力なメッセージ発信と現場巻き込みの双方を行うことです。
トップがDXの重要性を繰り返し訴え、変革への覚悟を示すことで社員の意識も変わります。同時に、現場のキーパーソンとなる管理職やリーダー層を巻き込み、彼らが先頭に立ってDX推進の旗振り役となるよう促します。
変化に対する不安を取り除くには、小さな成功体験を提供することも大切です。先に述べたようなPoCの成功事例や、社内の現場社員がDXで活躍した事例を社内報やミーティングで紹介し、「自分たちにもできる」という自信と前向きな雰囲気を醸成しましょう。
現場からボトムアップで業務改善アイデアが出てくる風土や、部門を超えたチームワークはDX成功の土壌となります。こうした文化を育てるには、日頃から社員のチャレンジを奨励し、失敗を責めず学びに変える姿勢を経営層が示すことが重要です。
チェンジマネジメントの専門手法としては、ステークホルダー分析やコミュニケーション計画の策定などがあります。DXによって影響を受ける部署や人に対し、早い段階から意見を聞き巻き込むことで抵抗を減らします。定期的な説明会やワークショップを開き、現場の声をプロジェクトに反映させると「自分ごと化」につながります。
加えて、人事制度面でDX推進を後押しするのも有効です。DXに貢献した社員を評価・報酬に反映したり、学習する社員を奨励する制度(例:資格取得支援や学習休暇の導入)を整えることで、変革へのコミットメントを組織全体で高めることができます。
実務直結の研修設計とリスキリング戦略
DX人材を育成する上で肝となるのが、研修(トレーニング)の設計です。従来型の座学中心の研修だけでは、実務で使えるスキルは身につきにくいものです。ここでは、研修と実務を結び付け効果を最大化する学習設計のポイントを紹介します。
研修と実務の乖離を埋めるには
前述のように、多くの企業が研修内容と実務のミスマッチに悩んでいます。この乖離を無くすためには、研修設計時にビジネス目標と直結させることが重要です。具体的には以下の工夫が考えられます。
業務課題をベースにしたカリキュラム
研修内容を決める際、汎用的な内容ではなく自社の具体的な業務課題を題材に取り入れます。例えば「在庫管理の精度向上」という課題があるなら、それをケーススタディにしたデータ分析研修を行う、といった形です。
受講者は自分たちの仕事の延長線上で学べるため、理解も深まり実践しやすくなります。研修設計段階で、現場の要件ヒアリングを行い目的と手段の整合性を取ることがポイントです。
アウトプット前提の学習
単に講義を聞くだけでなく、必ずアウトプットを伴う学習活動を組み込みます。リスキリング研修で推奨されるのは「インプット3割:アウトプット7割」という黄金比です。例えば研修の中にミニプロジェクトやハンズオン演習を盛り込み、学んだ知識を使って実際に成果物を作る経験をさせます。
ITツール研修であれば、小さなアプリケーションを実際に作ってみる、データ分析研修なら自社データで簡易分析して結果を発表する、といった具合です。アウトプットの場としてハッカソン(短期集中開発イベント)や成果発表会を開催するのも効果的です。こうした実践的学習により、研修直後から仕事で使えるスキルが身につきます。
ピアラーニング(仲間と学び合い)
受講者同士がチームを組み、互いに協力しながら課題に取り組むピアラーニングを導入しましょう。仲間と試行錯誤する中で得られる学びは深く、モチベーションの維持にもつながります。
実際のプロジェクトもチームで遂行するものですから、研修段階からチームワークや横の繋がりを醸成しておく意義は大きいです。部門を超えたメンバーで研修チームを構成すれば、社内ネットワークの拡大にも寄与します。
コーチ・メンターによるフォロー
研修期間中および修了後に、受講者をサポートする仕組みを用意しましょう。プロのコーチや先輩社員がメンターとなり、1対1の面談や定期的な相談機会を設けます。学習につまずいていないか、不安や疑問はないかをヒアリングし、必要に応じて助言・モチベートします。
Reskilling Campのサービスではキャリアコーチやテクニカルコーチが受講者一人ひとりと定期的に面談し、学習の意味付けを本人のキャリアと結び付けて動機づけを図る仕掛けを取り入れています。このように人的なフォローを充実させることで、研修の挫折を防ぎ学習定着を高めます。
生成AI活用スキルも新たな柱に
最近ではChatGPTをはじめとする生成AIの登場により、新しいスキル領域が加わりました。調査によれば、企業の4割以上が「週1回以上、生成AIを業務で活用している」といいます。例えば文章作成の補助やデータ分析の自動化などにAIを使うケースが増えています。
出典:リスキリングレポート〜リスキリングによる報酬変化と生成AI(ChatGPT等)活用の最新状況〜【2025年3月版】_31P
しかし同時に、「検索エンジンの延長のような使い方しかできず効果を実感できていない」(45%)、「業務プロセスに組み込む方法が分からない」(30.9%)といった課題も報告されています。つまり、生成AIを有効活用する知識・スキルが現場で不足しているのです。DXを推進する上では、この生成AI活用スキルもリスキリングの重要テーマに据えるべきでしょう。
具体的には、AIに適切な指示(プロンプト)を与えるスキル、AIの出力を批判的に評価し編集するスキル、業務フローの中にAIツールを組み込むための業務設計スキルなどが挙げられます。こうした新スキル習得の研修プログラムもいち早く用意し、社員が最新テクノロジーを武器にできるよう支援することが、DXの成功を加速させます。
DX推進の失敗パターンと回避策
DXプロジェクトは多くの企業にとって未知の挑戦であり、つまずきがちなポイントも共通しています。ここでは、よくある失敗パターンをいくつか紹介し、その回避策を解説します。同じ轍を踏まないよう、事前に対策を講じましょう。
失敗パターン1: DXの目的やKPIが不明確なまま進めてしまう
例: とりあえずAIツールを導入してみたが、何をもって成功とするか定義しておらず、評価もされないままフェードアウトしてしまった。
背景: DXの取り組み自体が目的化し、本来解決すべき課題や期待する効果が明確になっていない。KPI未設定のため成果検証もできない。
回避策: 事前のゴール設定とKPI設計を徹底することです。DX導入前に「〇〇の業務コストを△%削減するためのAI導入」など、目的と言える状態を定義し、それに紐づくKPIを設定しましょう。
進行中も定期レビューを行い、「目的を見失っていないか」「指標は達成に向かっているか」を検証します。ゴールがブレそうになったら経営層が軌道修正するぐらいの姿勢で、目的意識を持続させることが大切です。
失敗パターン2: 現場の巻き込み不足による抵抗勢力の発生
例: IT部門主導で新システムを導入したが、現場社員から「使いにくい」「やらされ感がある」と不満が出て定着しなかった。
背景: DX推進プロジェクトが現場の意見を十分聞かずに進行し、ユーザビリティや業務実態を無視した施策になってしまった。また変革への不安を払拭できず抵抗が生じた。
回避策: 現場巻き込み型のプロジェクト運営をすることです。キーパーソンとなる現場のエキスパート社員を初期からプロジェクトメンバーに加え、意見を反映させます。ユーザー部門からのフィードバックを取り入れるアジャイル的手法も有効です。
また、導入時には使い方研修やヘルプデスク設置などサポートを手厚くし、「困ったら聞ける」環境を提供します。現場の不安や不満の声は早期に吸い上げ対策することで、抵抗感を和らげスムーズな定着につなげましょう。
失敗パターン3: 人材・スキル面の準備不足
例: 新システムは導入したものの、運用を担うIT人材が社内におらず外部任せ。トラブル時に迅速な対応ができなかった。
背景: DX推進計画時に、人材育成と体制構築の見積もりが甘かった。技術導入にフォーカスするあまり、運用・保守や継続的改善の担い手を育てる視点が抜け落ちていた。
回避策: DX戦略と人材戦略は車の両輪です。スキルアセスメントを事前に行い、どんな能力が社内に足りないかを洗い出しておきます。その上で計画的にリスキリング研修を実施し、内製できる範囲を徐々に広げましょう。
同時に、どうしても不足する高度スキルについては外部パートナーとの提携や採用も織り交ぜ、運用面が手薄にならない体制を構築します。重要システムについては担当者の複数名育成(属人化排除)を図ることも忘れずに。DX導入=終わりではなく、導入後に回す運用フェーズまで見据えて人材を手当てしておくことが成功には欠かせません。
失敗パターン4: 研修や施策が属人的で「やりっぱなし」になる
例: DX研修を実施したが受講者任せでフォローがなく、結局現場で活用されず終わってしまった。
背景: 組織としての関与が弱く、研修結果の現場適用を支援する仕組みがない。人材育成を個人の自主性に委ねてしまっている。
回避策: 前述のように、研修後のフォローアップ体制を整えることです。研修成果を業務目標に結びつけ、上司が部下のスキル活用状況をチェックする仕組みや、受講者同士の発表会の場を設け継続的にアウトプットを促すと良いでしょう。
また、成果が出るまでは外部コーチの支援を受けるなど、「やりっぱなし」にさせない工夫が必要です。
Reskilling Campが解決できること
自社だけでDX人材育成や研修設計を全て内製するのが難しい場合、外部パートナーの力を借りるのも賢明な選択です。パーソルイノベーション株式会社が提供する法人向けリスキリング支援サービス「Reskilling Camp(リスキリングキャンプ)」は、まさに企業のDX人材育成を包括的にサポートするサービスです。最後に、本サービスの特徴を紹介します。
確立されたデジタル人材育成メソッドでDX推進リーダーを育成
Reskilling CampはPDCAサイクルを活用した独自の育成メソッドを提供しています。
① Plan: 中期経営計画やDX戦略を踏まえ、具体的なデジタル人材像を明確化
② Do(設計): 自社の業務や組織課題に最適化したオーダーメイド型のカリキュラムを作成
③ Do(実施): テクニカルスキルとキャリア開発の両面で専門コーチが徹底伴走
④ Check: 効果を可視化するアセスメントや具体的なコーチフィードバックを提供
⑤ Act: 評価結果をもとにした次期施策の具体的提案、さらなる人材育成の定着化を支援
これにより、自社内に「事業を理解し、デジタル技術を駆使して価値創造をリードできるDX人材」を継続的に生み出せる環境を整えます。
DX推進リーダー育成が中計達成に直結する理由
中期経営計画で掲げる「既存事業の高度化」や「新規サービス創出」を実現するためには、外部任せではなく、社内にDXの実行ノウハウを蓄積し、変革をリードできる人材の存在が不可欠です。
社内にDX推進リーダーを育てることにより、以下が可能になります。
① 戦略と現場課題を的確に橋渡しできる
② DX推進を現場レベルで自律的に実行できる
③ 人材の定着とスキル継承を通じて投資のROIを最大化できる
結果として、中計KPI(売上高成長率、新規事業・サービス創出数など)の達成をより確実なものにします。
具体例として事例動画を公開しておりますので、ご覧ください。
人と組織の変革からDX成功の第一歩を
DX推進で重要になるのは「人」と「組織文化」。テクノロジーはあくまで手段であり、それを活かすも殺すも人次第。だからこそ、研修と実務を結び付け現場で使える人材を育てること、変革を推進する組織風土を醸成することが、DX成功のポイントになります。
まずは自社のDXロードマップを描き、人材育成の計画に着手することから始めましょう。小さくても構いません。現場での成功体験を積み重ねることで、社内の意識も変わり、DXの波は確実に広がっていきます。
その際、必要に応じて外部の力もうまく借りながら、最短距離で成果を出す工夫も大切です。重要なのは「継続して学び、挑戦し続ける組織」へと変わっていくことではないでしょうか。
DXの本質は単なるIT化ではなく、企業文化や働き方そのものの変革。そして人と組織の変革こそが、DX成功への第一歩です。社員一人ひとりの成長が組織の成長につながり、それがやがて大きな事業変革の果実をもたらすでしょう。